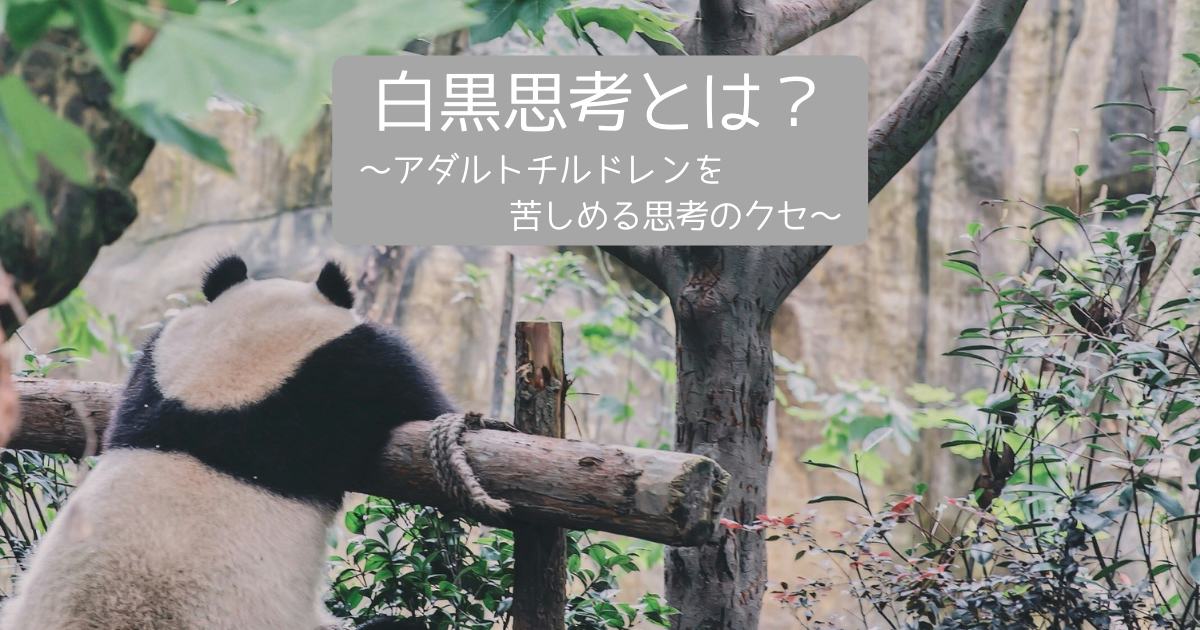世の中の多くのことは「白か黒」では判断できません。ただ、アダルトチルドレンはそんなあいまいさや不確実さが苦手だったりします。
アダルトチルドレンの生きづらさが強くなる考え方の1つが白黒思考です。
起きた出来事、人、自分に対して、何もかもハッキリさせなければと考える傾向が強いと、思い通りにならなかったり、不完全だと感じて落ち込むことが多くなります。
・小さなミスが許せない
・良いか悪いかで判断しがち
このような考え方をしがちな人は、白と黒では判断しきれないグレーを認める方法を参考にしてください。
肩の荷が少し軽くなり、「まぁ、いいか」と思える範囲が少し広がりますよ。

「白黒思考とは?」
白黒思考とは、グレーゾーンを認めない極端な考え方のことです。
「100点か0点か」「成功か失敗か」「愛されるか嫌われるか」など、物事を2つの極端な状態で認識してしまいます。
意見がハッキリしていて「良い」ことのように思える白黒思考。
しかし、過度に物事をハッキリさせようとする考え方は、人間関係がうまくいかなくなったり、生きづらさを増大させることにつがってしまうんです。

白黒思考が強い人の考え方の特徴

では、白黒思考が強い人はどのような考え方をしがちなのか見ていきましょう。
完璧主義
少しでもミスがあると「全部ダメだった」と思いこみやすく、自分にとても厳しい傾向があります。
「私はできる人間」or「私はダメな人間」など、自分の価値を極端に判断することもしばしば。
また、自分自身がストイックであるため、他者に対しても同様の頑張りや成果を求めがちになります。
ものすごく努力しているのですが、自分が目指す目標が非常に高いため、うまくいかないことにイライラしたり、落ち込んだりといった精神的負荷がかかりやすくなります。

グレーゾーンの評価が苦手
世の中には「できた・できなかった」「良かった・悪かった」だけでは測りきれないグレーゾーンのものがたくさん存在します。(むしろそういったものの方が多いです。)
しかし、白黒思考の人は「まぁまぁ良かった」「そこそこ頑張った」というグレーゾーンの評価が苦手。「できた!」という自己評価に達せなければ、頑張った過程があったとしても「何の意味もない…」と全てを否定し落ち込んでしまいます。

人を「いい人/悪い人」で分けてしまう
人は、様々な側面を持っています。
しかし、白黒思考の人は1つの言動でその人の全体像を決めつけてしまう傾向があります。
「あの人は本当に素晴らしい人だ」
「あの人は最悪の人間だ」
こんな風に「良いか悪いか」の判断になり、「悪いところもあるけど、良いところもあるよね」という考え方ができません。
また、良い人だと思っていた人に何か欠点を見つけてしまった場合、裏切られたような気がして一気にその人のことが嫌いになったり、関係を拒絶することもあります。

小さな失敗で全体を否定してしまう
白黒思考の人は、小さな失敗が許せない傾向が強いです。
1つのミスで、「これは私には向いてないんだ…」「やったことには1つも意味がなかった…」と全てを否定してしまいます。
あいまいな状況や不確実なものに強い不安を感じる
白黒思考の傾向が強いと、「はっきりしていない=悪いこと」と感じやすくなります。
そのため、あいまいな状況や不確実なものに出くわすと強いストレスを感じます。
柔軟に考えられない
白黒思考の人は、ひとつの正解に固執する傾向があります。
別の視点や考え方をなかなか受け入れられません。

疲れやすい、生きづらさを感じやすい
このように、白黒思考の人は自分や他人を追い詰めやすいため、プレッシャーや自己否定に苦しむことが多くなります。
その結果、うまくいかないことが増えたり、生きづらさを感じやすくなります。
しかし、うまくいかないということが受け入れられず「こんな自分はダメだ…」「もっと頑張らなくてはならない」という風に、さらに自分を追い込み続けてしまう場合も。
これではどんどん苦しくなってしまいますね。

白黒思考に陥る原因とは?

アダルトチルドレンは、なぜ白黒思考に陥りやすいのでしょうか?
①幼少期に「条件付きの愛情」を受けてきた
・「いい子にしていないと嫌われる」
・「勉強ができないと価値がない」
このように、「〇〇しないとダメ」「〇〇できなかったら価値がない」というメッセージを繰り返し受けていると、「OKかNG」といった極端な枠組みでしか物事を判断できなくなってしまいます。
②親も白黒思考だった
親自身が白黒思考の傾向が強かった場合、子どもも白黒思考になる可能性が高くなります。
・「テストは100点以外は意味がない」
・「1番でなければ価値がない」
こんな風に判断され続けると、次第に子どもも白か黒かの価値基準で物事を考えるようになります。

③安心できる「あいまいさ」を知らずに育った
本来であれば、親が
「失敗しても大丈夫だよ」
「うまくできなかったとしても、あなたのことを変わらず好きだよ」
という感情を子どもに伝えることで、子どもは安心感を得ます。
これは数値や「0か100か」といったハッキリした基準があるものではありません。
ただ、「なんとなく」「あいまい」であるとても大切な感情です。
しかし、アダルトチルドレンはこのようなあいまいな安心を得る経験をしていません。
いつも親の顔色をうかがい、
・「今はこうしたら怒られないかな」
・「多分、親はこう答えることを期待しているな」
といった、親の意をくむ答えを探すしかない状況で生きてきました。
そのため、あいまいさやグレーな状態が落ち着かず、不安を感じやすくなります。
そして何かしらの答えを導き出して、安心を得ようとするんですね。

白黒思考をやわらげる方法8選

では、白黒思考をやわらげるための方法をみていきましょう。
できそうな方法からぜひ試してみてくださいね。
①自分の言葉選びが極端になっていないかチェック✓
・「いつも○○だ!」
・「~~するべきだ」
・「~~にちがいない」
こんな言葉が頭の中に頻繁に浮かんだり、実際に使ったりしているときは白黒思考の傾向が強く出てきています。
最初は、自分の極端な考え方のクセに気づくだけでも大きな1歩です。
自分の中から出てくる考えをよく観察してみてくださいね。
②浮かんだ言葉をやわらかな表現に変えてみる
例えば、
→「いまくいかない時もあるよね」
・「100%」→「多くの場合は」
・「全部ダメだった」
→「うまくいかなかった部分もある」
こんな風に、似ている表現でも少し言葉を変えるだけでも断定のニュアンスがやわらぎます。
使う表現を少し柔らかくするだけで、思考も感情も少しずつ変化していきますよ。

③「グレーな選択肢」を意識的に探す
「完璧にできなかったからダメだ」という思考を、
・「今回はうまくいかなかったけど、次に活かそう」
・「取り組めた自分はすごいぞ」
④白黒思考に気づいたら、「60点でも十分!」と言葉に出す
・100点でなければ意味がない
・完璧でなければ価値がない
と考えてしまう時は、
・「60点でも十分!」
・「完璧じゃないけど、進んでいることがすごいよ!」
と声に出して言ってみてください。
最初はそう思えなくても、繰り返すうちにだんだんそんな気がしてきますよ。

⑤「○か×か」ではなく、「1〜10」で評価してみる
極端な2択ではなく、数値で考えると「まあまあ良かった」「悪くはなかった」という感覚を持ちやすくなります。
「今日は8くらい頑張れたかな?」
という風に、完璧か0か以外の評価方法を試してみましょう。
⑥良い面と悪い面のどちらも考える
1つのできごと・1人の人・自分に対して、良い面・悪い面どちらも考えるようにしてみましょう。
・あの人はずぼらだけど、おおらかだ。
・ジュースをこぼしたから掃除の手間が増えたけど、おかげで床がきれいになった。
⑦「もし同じことをしたのが友達だったらどう声をかけるか」を考える
自分に対して厳しすぎる人は、
「もし同じことをしたのが友達だったら、自分だったらどう声をかけるかな?」
と考えてみてください。
他人には優しい言葉がけや思いやりを持てるのに、自分に対してはやたらと厳しくなってしまうアダルトチルドレンが実は多いんです。
言葉が浮かんだら、そのセリフを自分自身にかけてあげてくださいね。

⑧できたことを見つけてほめる
白黒思考の人は、できていない部分に注目しがち。
ちょっとでもできたこと、少しでも進んだこと。
そんな小さな進歩に目を向け、ほめるようにしてみてくださいね。

まとめ
白黒思考は長年の思考のクセ。
いきなり変えようとしなくても大丈夫です。
でも、少しずつあいまいさやグレーゾーンを許す練習をしていくと、生きづらさが緩和されていきますよ。
自分の思考をまずは観察し、もし白黒思考だと気づいたらやわらげる方法をためしてみてくださいね。